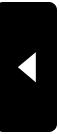2015年10月02日
おすすめシャンプーの秘密
COLORS独自の開拓ルートで出来る、おすすめシャンプーのラインナップが揃いました。
製品名は内緒ですが、ラインナップの一部「タナクラ クレイ入りシャンプー」の全成分の解説を致します☆
成分は、製品中に多く含まれている順に並べます。
とても多くの成分をご紹介致しますが、是非最後まで目を通して頂ければと思います☆
◎水
◎ココイルメチルアラニンNa(ラウロイルメチルアラニンNa)
一般名
ヤシ油脂肪酸メチルアラニンナトリウム液
効果・特性
ヤシ油脂肪酸とアラニンで作られるアミノ酸系界面活性剤。 アミノ酸系の中でも低刺激で安全性が高い。 適度な洗浄力・泡立ちがあり、グルタミンより洗浄力・泡立ちが良い。 さっぱりタイプで洗い上がりはふんわり・さらさらに仕上がる。COLORS的意見ですが、非常におすすめな洗浄剤の一つ

◎グリセリン
グリセリンは合成ものと天然ものがあります。合成物は石油系、天然はヤシの実由来です。
どちらがいいとか、どちらが悪いとか、ぶっちゃけありません。
植物由来というと、聞こえはいいですが、合成品のほうが純度は高いです。
価格もほとんどかわりません。
オーガニックを謳うのであれば、植物由来でしょうし、、
医療現場では当然、安定性の高い合成品を使います。
どちらがいいかは、もう宗教と同じです。
自分の信念を貫いてください。
グリセリンは植物、海藻、動物などに広く含まれるアルコールの一種です。
グリセロール(glycerol)とも呼ばれています。
もちろん、人間の体内にも存在し、中性脂肪として存在しています。
体の中性脂肪は、いったん脂肪酸とグリセリンに分解され、小腸で吸収されたのち、小腸壁で中性脂肪に再合成されます。
グリセリンと脂肪酸から構成される中性脂肪は、必要に応じてエネルギーに変わりますが、
普段は皮膚下や筋肉などに蓄えられています。
グリセリンフリー?! 意味あるの?
グリセリンフリーをウリにしている商品があるとのことで、ちょっと調べてみました。
グリセリンは99%の化粧品に使われているといっても過言ではありません。
もし・・・
「グリセリンが悪だ!」と消費者を洗脳できれば、化粧品業界で独り勝ちできますね。
ノンシリコンのように。
ご存じの通り、シリコンは無害であるどころか、痛んだ髪にはキューティクルとして働き、非常に有用な成分です。
シリコンを「悪」として、爆発的に売れたのがノンシリコンシャンプーです。
特に根拠があるわけではないのですが、見事なまでに、情報操作されたわけですね。
実際、化粧品の製造メーカーの人も、口を揃えていいます。
◎ヒドロキシアルキル(C12、14)
カルボキシベタイン型のプラスとマイナス(カチオンとアニオン)の両方の性質をもつ低刺激性の両性活性剤です。優れた起泡力と洗浄力をもち、カラーの褪色防止効果も高い活性剤です。
◎ラウリルグコシド
ラウリルグルコシドとは、天然成分を配合して作られる 植物由来の界面活性剤または洗浄剤として使われる成分です。
原材料はヤシ油やパーム核油に含まれるラウリン酸と、 糖の一種であるグルコースが結びつけることで生成される成分です。
主にシャンプー・ベビーシャンプーなどに配合されており、 類似成分としてはデシルグルコシドなどが挙げられます。
ラウリルグルコシドの効果・効能についてですが、 シャンプーに配合した場合は単体では泡立ちや洗浄力などについては 落ちるものの、肌への刺激を緩和する効果がある点が大きな特徴になります。
ラウリルグルコシドの安全性・毒性・注意点は、 一般的にラウリルの名称が付いたシャンプーの配合成分については避ける方も多く、 これは刺激が強く危険性もあるラウリル硫酸Naの存在が大きく関係しています。
ラウリル硫酸Naは、安価に製造できることでシャンプーには使われることも多いです。
刺激が強く毒性もある上に分子量が小さいことから肌内部にも浸透しやすく、 敏感肌の方や乾燥肌の方は避けるべき成分として広く知られています。
その一方で、ラウリルグルコシドの場合は名称は似ているものの原材料からして、 身体には優しく低刺激性の成分です。
人体への副作用の心配も無く、毒性もないとから 乳幼児向けのベビーシャンプーに配合されるなど、安全性が高い成分です。
ただ、ラウリルグルコシド単体では洗浄力や泡立ちが落ちます。
そのため、他に強い洗浄成分が配合されている可能性があり、 他の洗浄成分を確認しておく必要があります。
◎オキシヒドロキシプロピルアルギニンHCI
アミノ酸系の両性界面活性剤。
従来の第四級カチオン界面活性剤(~クロリド)よりも低刺激でほぼ同じ効果がある。毛髪に吸着し、帯電防止、柔軟性などの効果を発揮する。
PPTなどのトリートメント成分とは異なり、髪表面を整え一時的に質感をアップするものである。
皮膚や眼に穏和で生分解性にも優れている
◎ラウロイルシルクアミノ酸k
加水分解シルクとラウリン酸との縮合物。界面活性剤。 ラウロイル加水分解シルクNaの改良版で、泡がきめ細かく、分子量が小さくなって浸透しやすく改良された。 トリートメント効果が高く、毛髪や皮膚を優しく適度な脱脂力で洗浄する。保護、湿潤、柔軟効果を示し、特に毛髪を洗浄するにはこれ以上ない洗浄剤である。 私はこのシルクやコラーゲンのPPT洗浄剤がシャンプーにはベストだと考えています。 ただし非常に高価な成分である。
◎ジイソステアリン酸ポリグリセリル-10
植物から得られた脂肪酸のイソステアリン酸に、植物から得られるグリセリンを付加させた植物性の乳化剤。乳化作用のほか、高いエモリエント効果もあります。
メイク汚れを溶かし込んですっきり落とします。
◎タナクラクレイ
タナクラクレイとは、数千万年前古代地中(新第三系・中新統)で海洋動植物(魚類の各種ネクトン・プランクトン・藻類・海草其の他の生物類)が埋没 堆積し、微生物の働きで永い時間をかけ分解・代謝・再合成が繰り返され、各種ミネラルがバランスよく含有された海泥(軟質多孔性古代海洋腐食質)が地殻変 動で地上に突出した海泥層から採取した貴重な天然無機質資源です。
タナクラクレイの天然ミネラルを水に溶出すると水が高分子化されます。その大きさは47.4Hzで水道水の3分の1以下と言われています。ですから細胞の活性化に必要な天然ミネラルの栄養が細胞の奥まで浸透します。 「タナクレイ」は、抜群の浸透力が魅力の高分子・高機能・高天然ミネラル水をペースとした商品です。
古代海泥「タナクラクレイ」は、ヨーロッパ北海の海泥よりも多種類の天然ミネラルが含まれており上質で、現在分かっている天然ミネラル数は66種類を数えています。それに加え、イオン交換性能も抜群です。 タナクラクレイは、備長炭の数十倍の多孔質で、すばらしい吸着洗浄効果があります。その孔の大きさは500Å(100万/1mm)で小さな汚れも吸着いたします。

◎ジステアリン酸グリコール
シャンプーに光沢を与え、増粘させる。 市販のシャンプーに良く配合されており、液体が白く、光沢があるのはこの成分による効果。 保湿や補修等の髪に対しての効果は無い。
◎ポリクオタニウム-10
植物からとれる多糖類(セルロース)にプラスイオンをくっつけ柔軟性に優れたコンディショニング剤となっています。
髪への吸着性に優れ、頭皮や髪を保湿する効果があり、シャンプー時のきしみを防ぎます。
ポリクオタニウム―10は毛髪や頭皮に吸着しますが、シャンプーを行なった際に流れるため、人体への刺激性などは特になく、シリコンよりも安全が高いとされています。
よくシリコンと間違われることがありますが、基本構造は植物繊維であり、シリコン系の物質でないため、全くの別物です。
◎アルキル(C12、14)オキシヒドロキシプロピルアルギニンHCI
アミノ酸系の両性界面活性剤。
従来の第四級カチオン界面活性剤(~クロリド)よりも低刺激でほぼ同じ効果がある。毛髪に吸着し、帯電防止、柔軟性などの効果を発揮する。
PPTなどのトリートメント成分とは異なり、髪表面を整え一時的に質感をアップするものである。
皮膚や眼に穏和で生分解性にも優れている。
◎ステアリルトリモニウムサッカリン
帯電防止剤、ヘアコンディショニング剤
シャンプーのコンディショニング効果を高める働きがある。
◎DPG
PG(プロピレングリコール)を製造する際の副産物として生じる成分です。PGは麺類などの食品添加物のひとつとしても知られています。
DPGもPGに似た性質を持ちますが、PGに比べて粘度や溶解力が高い素材となっています。
水はもちろん天然樹脂やニトロセルロース、ヒマシ油といった油脂にも溶けやすいため、その扱いやすさから、化粧品成分としても幅広く用いられています。
保湿性は高いもののべたつき感は少ないため、比較的サラっとしたみずみずしさのある化粧水に用いられることが多い成分と言えます。
伸びや滑りをよくする感触改良剤以外にも、乳化剤、殺菌剤、溶剤などとしての役割を果たすことから、基礎化粧品やメイクアップ化粧品ほかヘアケア製品や医薬品にも用いられています。
◎イソステアロイル乳酸Na
乳化剤の一種で、安全性が極めて高く、皮膚や毛髪のたんぱく質に作用して、柔軟性を向上させて優れた感触を与えます。石鹸やシャンプー、染毛剤等に広く利用されている成分です。
◎クレアチン
動物の体内に存在するたんぱく質です。したがって、あまり聞かない名前かもしれませんが、人工化合物等ではありません。もともと人間の体の中に存在し、アルギニン、メチオニン、グリシンといったアミノ酸から合成されるものです。
◎ラフィノース
主に植物性ソースの保湿・乳化・肌質向上剤です。オプションでこれらを加えただけでも高価になる既製品が沢山ありますが、自作すると意外に安価に出来るものです。基本的に無添加のものをセレクトしており化学防腐剤などは一切入っていない化粧品原料となっております。
◎グリコシルトレハロース
主に植物性ソースの保湿・乳化・肌質向上剤です。オプションでこれらを加えただけでも高価になる既製品が沢山ありますが、基本的に無添加のものをセレクトしており化学防腐剤などは一切入っていない化粧品原料となっております。
グリコシルトレハロースとは、とうもろこし由来の天然の糖質とグルコースが結合したものです。代謝の促進や保湿、保護、抗炎症、日焼けの防止、美白、肌荒れの改善としての効果を持つ成分であるとされています。
グリコシルトレハロースの名前にも含まれているトレハロースは元来、砂漠に生息する植物に含まれていたものです。砂漠の植物は長期間の乾燥に晒されたとしても、再び水分が与えられれば即座にみずみずしさを取り戻すという強靭な生命力を持っていました。
この生命力の源こそがトレハロースであるといわれており、皮膚上でも同じような効果を発揮させるために作り出された成分がグリコシルトレハロースなのです。
◎イソス加水分解水添デンプン
原材料: トウモロコシデンプン
酵素反応させたデンプンに水素を添加して得られます。保湿性に優れるほか、抗炎症、紫外線による細胞ダメージを保護すると言われています。感触向上剤としても用いられます。
◎ヘマチン
ヘマチンはグロビンと結合して血液の主成分であるヘモグロビンを形成しています。
ヘ マチンとは、血液中のヘモグロビンを電気的に分離して「ヘマチン」と「グロビン」に分けたものです。 このへマチンはグロビンと離れている状態だと非常に不安定で、何かに結合しようとします。 毛髪の成分ケラチンが、血液のグロビンと似ているため、ヘマチンを毛髪につけるとケラチンがグロビンと分子構造が非常に似ているため、とても強力に結合し 傷んだ毛髪を修復します。
◎各エキス
タチジャコウソウ花/葉エキス
香料、皮膚コンディショニング剤
ローズマリー葉エキス
消炎、収れん、血行促進、抗菌、殺菌、抗酸化
セージ葉エキス
消炎効果、酸化防止、殺菌効果、育毛効果
ビルベリーエキス
眼精疲労や視力回復,強力な抗酸化,毛細血管の保護
◎エタノール
エタノールは、デンプンや糖蜜をアルコール発酵させたり、エチレンから化学合成したりして作られます。別名を酒精と言うことからも分かるように、お酒に含まれる成分です。アルコール度数の高いウォッカやホワイトリカーはエタノールの代用品になることもあります。
エタノールの用途といえば「消毒用」。でも、水分を含まない無水アルコールに殺菌作用はなく、水で薄めて初めて殺菌作用を持ちます。そうして調整し た消毒用アルコールは、冷蔵庫内や水回りなど衛生面が気になる場所の掃除に最適。揮発性なので、家電など水を使えないものにも使えます。水にも油にも溶け るという変わった性質も持っているので、手作り化粧品や消臭スプレーなど作るときにも重宝されます。
◎クエン酸
健康食品などとして幅広く知られている物ですが、整髪料などには酸化防止剤として使われている。
◎ラベンダー油
抗炎症、抗菌、日焼け防止、殺菌、香料としての働きがある。
◎ペンチレングリコール
適度の保湿性と抗菌力のある無色無臭の保湿成分です。グルセリンよりさっぱりした使用感で感触改良剤として使用します。
◎イソプロパノール
エタノールに極めて類似しているが、エタノールより強い殺菌力を持つ。
◎フェノキシエタノール
玉露の揮発成分として発見されたフェノキシエタノールは、高い殺菌効果を持っているため、防腐剤・殺菌剤として化粧品などに配合されるアルコール成分です。パラベンに比べると比較的新しい防腐剤で、旧表示指定成分には該当しません。しかし、殺菌力が強いために配合量は製品中1%以内と、制限されています。
天然のチョウジエキスなどの天然防腐剤が添加した化粧品の方が安全かと思われますが、場合によって肌が老化して見えてしまうシミ・シワ、さらにはたるみなどの原因となってしまう場合もあります。それは天然防腐剤によって肌の酸化が起きてしまうからです。つまり天然防腐剤よりもフェノキシエタノール等の化学防腐剤の方が安全で、逆に天然防腐剤は重大な肌のダメージを受けてしまう場合もあるのです。防腐剤と聞くと身体に悪いイメージしかありませんが、そんな中でも天然といった言葉などに騙されず、それぞれの特徴をしっかりと理解して上手くそれらを利用し、肌に与えるダメージを少なくしていきましょう。
◎メチルパラベン
抗菌作用が強く防腐剤として化粧品に使用されるパラベンの中で、一番肌への刺激が少ないとされているのがメチルパラベンです。
パラベンに比べて抗菌作用は劣りますが、低刺激ということで現在多くの化粧品に防腐剤として配合されています。
◎香料
私たちの住む地球には多くの香りに満ち溢れています。植物は香りで昆虫を誘ったり、動物たちも香りで種の保存を図ったりします。人間も、食べ物の香りに食欲を刺激されたり、木々の香りで季節の移り変わりを感じたりと、香りからさまざまな刺激や情報を得ています。もし世界に香 りがなかったら。私たちの生活はなんと味気ないものになることでしょう。人間の生活と香りは切っても切れない不可欠なものとなっています。嗅覚を刺激する主に自然界に発生するにおいを「香り」、主に商業目的で製造販売される香気を持った有機化学物質またはそれらの集合体を「香料」としています。
製品名は内緒ですが、ラインナップの一部「タナクラ クレイ入りシャンプー」の全成分の解説を致します☆
成分は、製品中に多く含まれている順に並べます。
とても多くの成分をご紹介致しますが、是非最後まで目を通して頂ければと思います☆
◎水
◎ココイルメチルアラニンNa(ラウロイルメチルアラニンNa)
一般名
ヤシ油脂肪酸メチルアラニンナトリウム液
効果・特性
ヤシ油脂肪酸とアラニンで作られるアミノ酸系界面活性剤。 アミノ酸系の中でも低刺激で安全性が高い。 適度な洗浄力・泡立ちがあり、グルタミンより洗浄力・泡立ちが良い。 さっぱりタイプで洗い上がりはふんわり・さらさらに仕上がる。COLORS的意見ですが、非常におすすめな洗浄剤の一つ

◎グリセリン
グリセリンは合成ものと天然ものがあります。合成物は石油系、天然はヤシの実由来です。
どちらがいいとか、どちらが悪いとか、ぶっちゃけありません。
植物由来というと、聞こえはいいですが、合成品のほうが純度は高いです。
価格もほとんどかわりません。
オーガニックを謳うのであれば、植物由来でしょうし、、
医療現場では当然、安定性の高い合成品を使います。
どちらがいいかは、もう宗教と同じです。
自分の信念を貫いてください。
グリセリンは植物、海藻、動物などに広く含まれるアルコールの一種です。
グリセロール(glycerol)とも呼ばれています。
もちろん、人間の体内にも存在し、中性脂肪として存在しています。
体の中性脂肪は、いったん脂肪酸とグリセリンに分解され、小腸で吸収されたのち、小腸壁で中性脂肪に再合成されます。
グリセリンと脂肪酸から構成される中性脂肪は、必要に応じてエネルギーに変わりますが、
普段は皮膚下や筋肉などに蓄えられています。
グリセリンフリー?! 意味あるの?
グリセリンフリーをウリにしている商品があるとのことで、ちょっと調べてみました。
グリセリンは99%の化粧品に使われているといっても過言ではありません。
もし・・・
「グリセリンが悪だ!」と消費者を洗脳できれば、化粧品業界で独り勝ちできますね。
ノンシリコンのように。
ご存じの通り、シリコンは無害であるどころか、痛んだ髪にはキューティクルとして働き、非常に有用な成分です。
シリコンを「悪」として、爆発的に売れたのがノンシリコンシャンプーです。
特に根拠があるわけではないのですが、見事なまでに、情報操作されたわけですね。
実際、化粧品の製造メーカーの人も、口を揃えていいます。
◎ヒドロキシアルキル(C12、14)
カルボキシベタイン型のプラスとマイナス(カチオンとアニオン)の両方の性質をもつ低刺激性の両性活性剤です。優れた起泡力と洗浄力をもち、カラーの褪色防止効果も高い活性剤です。
◎ラウリルグコシド
ラウリルグルコシドとは、天然成分を配合して作られる 植物由来の界面活性剤または洗浄剤として使われる成分です。
原材料はヤシ油やパーム核油に含まれるラウリン酸と、 糖の一種であるグルコースが結びつけることで生成される成分です。
主にシャンプー・ベビーシャンプーなどに配合されており、 類似成分としてはデシルグルコシドなどが挙げられます。
ラウリルグルコシドの効果・効能についてですが、 シャンプーに配合した場合は単体では泡立ちや洗浄力などについては 落ちるものの、肌への刺激を緩和する効果がある点が大きな特徴になります。
ラウリルグルコシドの安全性・毒性・注意点は、 一般的にラウリルの名称が付いたシャンプーの配合成分については避ける方も多く、 これは刺激が強く危険性もあるラウリル硫酸Naの存在が大きく関係しています。
ラウリル硫酸Naは、安価に製造できることでシャンプーには使われることも多いです。
刺激が強く毒性もある上に分子量が小さいことから肌内部にも浸透しやすく、 敏感肌の方や乾燥肌の方は避けるべき成分として広く知られています。
その一方で、ラウリルグルコシドの場合は名称は似ているものの原材料からして、 身体には優しく低刺激性の成分です。
人体への副作用の心配も無く、毒性もないとから 乳幼児向けのベビーシャンプーに配合されるなど、安全性が高い成分です。
ただ、ラウリルグルコシド単体では洗浄力や泡立ちが落ちます。
そのため、他に強い洗浄成分が配合されている可能性があり、 他の洗浄成分を確認しておく必要があります。
◎オキシヒドロキシプロピルアルギニンHCI
アミノ酸系の両性界面活性剤。
従来の第四級カチオン界面活性剤(~クロリド)よりも低刺激でほぼ同じ効果がある。毛髪に吸着し、帯電防止、柔軟性などの効果を発揮する。
PPTなどのトリートメント成分とは異なり、髪表面を整え一時的に質感をアップするものである。
皮膚や眼に穏和で生分解性にも優れている
◎ラウロイルシルクアミノ酸k
加水分解シルクとラウリン酸との縮合物。界面活性剤。 ラウロイル加水分解シルクNaの改良版で、泡がきめ細かく、分子量が小さくなって浸透しやすく改良された。 トリートメント効果が高く、毛髪や皮膚を優しく適度な脱脂力で洗浄する。保護、湿潤、柔軟効果を示し、特に毛髪を洗浄するにはこれ以上ない洗浄剤である。 私はこのシルクやコラーゲンのPPT洗浄剤がシャンプーにはベストだと考えています。 ただし非常に高価な成分である。
◎ジイソステアリン酸ポリグリセリル-10
植物から得られた脂肪酸のイソステアリン酸に、植物から得られるグリセリンを付加させた植物性の乳化剤。乳化作用のほか、高いエモリエント効果もあります。
メイク汚れを溶かし込んですっきり落とします。
◎タナクラクレイ
タナクラクレイとは、数千万年前古代地中(新第三系・中新統)で海洋動植物(魚類の各種ネクトン・プランクトン・藻類・海草其の他の生物類)が埋没 堆積し、微生物の働きで永い時間をかけ分解・代謝・再合成が繰り返され、各種ミネラルがバランスよく含有された海泥(軟質多孔性古代海洋腐食質)が地殻変 動で地上に突出した海泥層から採取した貴重な天然無機質資源です。
タナクラクレイの天然ミネラルを水に溶出すると水が高分子化されます。その大きさは47.4Hzで水道水の3分の1以下と言われています。ですから細胞の活性化に必要な天然ミネラルの栄養が細胞の奥まで浸透します。 「タナクレイ」は、抜群の浸透力が魅力の高分子・高機能・高天然ミネラル水をペースとした商品です。
古代海泥「タナクラクレイ」は、ヨーロッパ北海の海泥よりも多種類の天然ミネラルが含まれており上質で、現在分かっている天然ミネラル数は66種類を数えています。それに加え、イオン交換性能も抜群です。 タナクラクレイは、備長炭の数十倍の多孔質で、すばらしい吸着洗浄効果があります。その孔の大きさは500Å(100万/1mm)で小さな汚れも吸着いたします。

◎ジステアリン酸グリコール
シャンプーに光沢を与え、増粘させる。 市販のシャンプーに良く配合されており、液体が白く、光沢があるのはこの成分による効果。 保湿や補修等の髪に対しての効果は無い。
◎ポリクオタニウム-10
植物からとれる多糖類(セルロース)にプラスイオンをくっつけ柔軟性に優れたコンディショニング剤となっています。
髪への吸着性に優れ、頭皮や髪を保湿する効果があり、シャンプー時のきしみを防ぎます。
ポリクオタニウム―10は毛髪や頭皮に吸着しますが、シャンプーを行なった際に流れるため、人体への刺激性などは特になく、シリコンよりも安全が高いとされています。
よくシリコンと間違われることがありますが、基本構造は植物繊維であり、シリコン系の物質でないため、全くの別物です。
◎アルキル(C12、14)オキシヒドロキシプロピルアルギニンHCI
アミノ酸系の両性界面活性剤。
従来の第四級カチオン界面活性剤(~クロリド)よりも低刺激でほぼ同じ効果がある。毛髪に吸着し、帯電防止、柔軟性などの効果を発揮する。
PPTなどのトリートメント成分とは異なり、髪表面を整え一時的に質感をアップするものである。
皮膚や眼に穏和で生分解性にも優れている。
◎ステアリルトリモニウムサッカリン
帯電防止剤、ヘアコンディショニング剤
シャンプーのコンディショニング効果を高める働きがある。
◎DPG
PG(プロピレングリコール)を製造する際の副産物として生じる成分です。PGは麺類などの食品添加物のひとつとしても知られています。
DPGもPGに似た性質を持ちますが、PGに比べて粘度や溶解力が高い素材となっています。
水はもちろん天然樹脂やニトロセルロース、ヒマシ油といった油脂にも溶けやすいため、その扱いやすさから、化粧品成分としても幅広く用いられています。
保湿性は高いもののべたつき感は少ないため、比較的サラっとしたみずみずしさのある化粧水に用いられることが多い成分と言えます。
伸びや滑りをよくする感触改良剤以外にも、乳化剤、殺菌剤、溶剤などとしての役割を果たすことから、基礎化粧品やメイクアップ化粧品ほかヘアケア製品や医薬品にも用いられています。
◎イソステアロイル乳酸Na
乳化剤の一種で、安全性が極めて高く、皮膚や毛髪のたんぱく質に作用して、柔軟性を向上させて優れた感触を与えます。石鹸やシャンプー、染毛剤等に広く利用されている成分です。
◎クレアチン
動物の体内に存在するたんぱく質です。したがって、あまり聞かない名前かもしれませんが、人工化合物等ではありません。もともと人間の体の中に存在し、アルギニン、メチオニン、グリシンといったアミノ酸から合成されるものです。
◎ラフィノース
主に植物性ソースの保湿・乳化・肌質向上剤です。オプションでこれらを加えただけでも高価になる既製品が沢山ありますが、自作すると意外に安価に出来るものです。基本的に無添加のものをセレクトしており化学防腐剤などは一切入っていない化粧品原料となっております。
◎グリコシルトレハロース
主に植物性ソースの保湿・乳化・肌質向上剤です。オプションでこれらを加えただけでも高価になる既製品が沢山ありますが、基本的に無添加のものをセレクトしており化学防腐剤などは一切入っていない化粧品原料となっております。
グリコシルトレハロースとは、とうもろこし由来の天然の糖質とグルコースが結合したものです。代謝の促進や保湿、保護、抗炎症、日焼けの防止、美白、肌荒れの改善としての効果を持つ成分であるとされています。
グリコシルトレハロースの名前にも含まれているトレハロースは元来、砂漠に生息する植物に含まれていたものです。砂漠の植物は長期間の乾燥に晒されたとしても、再び水分が与えられれば即座にみずみずしさを取り戻すという強靭な生命力を持っていました。
この生命力の源こそがトレハロースであるといわれており、皮膚上でも同じような効果を発揮させるために作り出された成分がグリコシルトレハロースなのです。
◎イソス加水分解水添デンプン
原材料: トウモロコシデンプン
酵素反応させたデンプンに水素を添加して得られます。保湿性に優れるほか、抗炎症、紫外線による細胞ダメージを保護すると言われています。感触向上剤としても用いられます。
◎ヘマチン
ヘマチンはグロビンと結合して血液の主成分であるヘモグロビンを形成しています。
ヘ マチンとは、血液中のヘモグロビンを電気的に分離して「ヘマチン」と「グロビン」に分けたものです。 このへマチンはグロビンと離れている状態だと非常に不安定で、何かに結合しようとします。 毛髪の成分ケラチンが、血液のグロビンと似ているため、ヘマチンを毛髪につけるとケラチンがグロビンと分子構造が非常に似ているため、とても強力に結合し 傷んだ毛髪を修復します。
◎各エキス
タチジャコウソウ花/葉エキス
香料、皮膚コンディショニング剤
ローズマリー葉エキス
消炎、収れん、血行促進、抗菌、殺菌、抗酸化
セージ葉エキス
消炎効果、酸化防止、殺菌効果、育毛効果
ビルベリーエキス
眼精疲労や視力回復,強力な抗酸化,毛細血管の保護
◎エタノール
エタノールは、デンプンや糖蜜をアルコール発酵させたり、エチレンから化学合成したりして作られます。別名を酒精と言うことからも分かるように、お酒に含まれる成分です。アルコール度数の高いウォッカやホワイトリカーはエタノールの代用品になることもあります。
エタノールの用途といえば「消毒用」。でも、水分を含まない無水アルコールに殺菌作用はなく、水で薄めて初めて殺菌作用を持ちます。そうして調整し た消毒用アルコールは、冷蔵庫内や水回りなど衛生面が気になる場所の掃除に最適。揮発性なので、家電など水を使えないものにも使えます。水にも油にも溶け るという変わった性質も持っているので、手作り化粧品や消臭スプレーなど作るときにも重宝されます。
◎クエン酸
健康食品などとして幅広く知られている物ですが、整髪料などには酸化防止剤として使われている。
◎ラベンダー油
抗炎症、抗菌、日焼け防止、殺菌、香料としての働きがある。
◎ペンチレングリコール
適度の保湿性と抗菌力のある無色無臭の保湿成分です。グルセリンよりさっぱりした使用感で感触改良剤として使用します。
◎イソプロパノール
エタノールに極めて類似しているが、エタノールより強い殺菌力を持つ。
◎フェノキシエタノール
玉露の揮発成分として発見されたフェノキシエタノールは、高い殺菌効果を持っているため、防腐剤・殺菌剤として化粧品などに配合されるアルコール成分です。パラベンに比べると比較的新しい防腐剤で、旧表示指定成分には該当しません。しかし、殺菌力が強いために配合量は製品中1%以内と、制限されています。
天然のチョウジエキスなどの天然防腐剤が添加した化粧品の方が安全かと思われますが、場合によって肌が老化して見えてしまうシミ・シワ、さらにはたるみなどの原因となってしまう場合もあります。それは天然防腐剤によって肌の酸化が起きてしまうからです。つまり天然防腐剤よりもフェノキシエタノール等の化学防腐剤の方が安全で、逆に天然防腐剤は重大な肌のダメージを受けてしまう場合もあるのです。防腐剤と聞くと身体に悪いイメージしかありませんが、そんな中でも天然といった言葉などに騙されず、それぞれの特徴をしっかりと理解して上手くそれらを利用し、肌に与えるダメージを少なくしていきましょう。
◎メチルパラベン
抗菌作用が強く防腐剤として化粧品に使用されるパラベンの中で、一番肌への刺激が少ないとされているのがメチルパラベンです。
パラベンに比べて抗菌作用は劣りますが、低刺激ということで現在多くの化粧品に防腐剤として配合されています。
◎香料
私たちの住む地球には多くの香りに満ち溢れています。植物は香りで昆虫を誘ったり、動物たちも香りで種の保存を図ったりします。人間も、食べ物の香りに食欲を刺激されたり、木々の香りで季節の移り変わりを感じたりと、香りからさまざまな刺激や情報を得ています。もし世界に香 りがなかったら。私たちの生活はなんと味気ないものになることでしょう。人間の生活と香りは切っても切れない不可欠なものとなっています。嗅覚を刺激する主に自然界に発生するにおいを「香り」、主に商業目的で製造販売される香気を持った有機化学物質またはそれらの集合体を「香料」としています。
2015年10月01日
界面活性剤とシリコン
シャンプーの成分は、90%以上が水と界面活性剤で構成されています。
界面活性剤は、洗浄効果を期待して配合されている成分です。シャンプー剤に配合されている界面活性剤は大きく5つに分類することができます。
高級アルコール系界面活性剤
アミノ酸系界面活性剤
ベタイン系界面活性剤(両イオン性界面活性剤)
ノニオン界面活性剤(非イオン性界面活性剤)
天然界面活性剤
界面活性剤の中には洗浄力の強いものと弱いものがありますが、洗浄力の強い界面活性剤は、色々と問題があります。
例えば、
◎頭皮や髪への刺激が強い⇒薄毛、頭皮の荒れの原因になる。
◎ 一緒に配合されている成分の効能をかき消してしまう。
◎ 頭皮の脂を取り過ぎてしまうので、不足した脂を補うため皮脂の分泌が盛んになる⇒結果、表面は脂ぎっているのに頭皮は乾燥している状態に⇒薄毛、頭皮の荒れの原因になる。
シャンプーは 水と界面活性剤でできているわけですから、シャンプー選びでもっとも大切なのは「どんな界面活性剤が使われているか」といっても過言ではありません。
では、以上に挙げた界面活性剤のうち、「洗浄力の強い界面活性剤」「適度な洗浄力の界面活性剤」はどれなのでしょう?
まずは界面活性剤の種類について、解説していきます。
高級アルコール系界面活性剤
市販の安価なシャンプーには、非常に洗浄力の強い高級アルコール系界面活性剤が配合されていることが多いです。
代表的なのが、
◎ラウレス硫酸Na
◎ラウリル硫酸Na
これらは、ヤシ油などに含まれるラウリン酸を原料にして作られた界面活性剤で生成過程で硫酸が使われます。
硫酸は非常に強い酸-皮膚や髪(タンパク質)を変性させてしまう刺激の強い成分です。また、洗浄力も強いため、頭皮の皮脂を過剰に除去してしまいます。
皮脂を過剰に除去してしまうと、頭皮は足りなくなった皮脂を補うために更に皮脂を分泌するようになり、その皮脂をまた除去して…という悪循環に陥ってしまうのですが、これが薄毛や頭皮の荒れの原因にもなるのです。
女性の場合、更年期に薄毛の悩みを抱える方も多いと思うのですが、薄毛が気になるなら ラウレス硫酸Naやラウリル硫酸Naが配合されているシャンプーは避けるべきでしょう。
ちなみに、同じくラウリン酸を原料にして作られた、
◎ラウレス-4カルボン酸Na
◎ラウレス-4酢酸Na
この2つは硫酸ではなく、弱い酸であるカルボン酸や酢酸(お酢)を使って生成されたものなので、比較的洗浄力もマイルドで刺激も弱い高級アルコール系界面活性剤です。
アミノ酸系界面活性剤
髪の90%はケラチンというタンパク質からできています。また、ケラチンというタンパク質は18種類のアミノ酸で構成されています。
◎ココイルグルタミン酸
◎ココイルアラニン
以上のように、成分名の中にアミノ酸の名前が含まれている界面活性剤はアミノ酸を原料として作られています。
グルタミン酸はケラチンの約13.7%、アラニンは2.8%を占めるアミノ酸です。
グルタミン酸には、他のアミノ酸の合成を助ける働きや髪のダメージ部分に吸着しコンディショニング効果を高める働き、またアラニンにはキューティクルが開かないようにする働き、頭皮のバリア機能を高める働きがあります。
ちなみに「ココイル」とは「ヤシ油から抽出した脂肪酸を用いている」という意味で、ココイルグルタミン酸の場合、ヤシ油から抽出した脂肪酸とグルタミン酸を原料にして作られた界面活性剤ということになります。
アミノ酸系界面活性剤は、髪の毛を構成するアミノ酸由来の成分に由来しているため、マイルドに洗い上げることができます。
ベタイン系界面活性剤(両イオン性界面活性剤)
◎ラウラミドプロピルベタイン
◎コカミドプロピルベタイン
成分名に「ベタイン」がついたものは、ベタイン系界面活性剤と呼ばれています。
別名 両イオン性界面活性剤とも呼ばれていて、その名の通り水に溶けると陰イオンにも陽イオンにもなる性質を持っています。
水がアルカリ性の場合は陰イオンに、酸性の場合は陽イオンになることで、水中の酸やアルカリを中和し、この作用により他の界面活性剤の洗浄力を低下させないようにする働きが期待できます。
そのため単独で配合されることはほとんどなく、他の界面活性剤の洗浄力を落とさないための補助剤として使用されることが多い界面活性剤です。
また、アミノ酸系界面活性剤より洗浄力が弱い分、刺激も弱いため皮膚の弱い方にもオススメできる界面活性剤です。
最近では、
◎ラウリルヒドロキシスルタイン
◎ラウラミドプロピルヒドロキシスルタイン
など、スルタイン系の両イオン性界面活性剤も見られるようになりました。(性質は、ベタイン系界面活性剤とほとんど同じです。)
ノニオン界面活性剤(非イオン性界面活性剤)
一番見分けにくいのが、このノニオン界面活性剤です。
代表的なものは、コカミドDEA のように、成分名の最後に「EA(エタノールアミンの略)」が付きます。
また、界面活性作用のある配糖体(糖を元にして作られた物質)を加えて、泡立ちを良くしている製品もありますが、これもノニオン界面活性剤に分類されます。
洗浄効果は穏やかで、水の硬度による影響を受けないため、メインの界面活性剤として配合されるよりも他の界面活性剤の補助的な役割で配合されることが多いようです。
天然界面活性剤
天然由来の界面活性剤には、
◎レシチン
◎サポニン
などがあります。
レシチンは卵黄に、サポニンは人参やヘチマやお茶に含まれている成分です。
天然由来の成分なので、比較的頭皮への刺激も弱く、これらの界面活性剤が配合されているシャンプーはマイルドな洗い心地となっています。
卵黄は良質なタンパク質からできているため、インドのアーユルヴェーダでは卵黄を頭皮に塗り、栄養を与えながら過剰な脂を取るという方法もあるくらいです。
また、界面活性作用はありませんが、殺菌作用のあるローズウォーターや洗浄力のあるクレイ(泥)が天然界面活性剤の代わりに配合されることもあります。
注意すべきはラウレス硫酸Na、ラウリル硫酸Na
今まで紹介した界面活性剤のうち、避けたほうがいいのは「高級アルコール系界面活性剤」です。
中でも、
◎ラウレス硫酸Na
◎ラウリル硫酸Na
この2つが配合されているシャンプーは要注意。
一般的に、この2つを「合成界面活性剤」と読んでいて、
合成界面活性剤 = ラウレス硫酸Naやラウリル硫酸Na = 頭皮、髪に悪い
と、私は考えています。
(厳密に言うと、高級アルコール系界面活性剤、アミノ酸系界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、ノニオン界面活性剤は全て「合成界面活性剤」に分類されるのですが、一般的に「合成界面活性剤 = ラウレス硫酸Naやラウリル硫酸Na」という認識が浸透しているようです。)
また、ラウレス硫酸Naやラウリル硫酸Naは「石油から作られた界面活性剤」と言われることもあります。
これらの界面活性剤の原料になるラウリン酸が石油を精製する際に分留される物質だからです。
しかし、界面活性剤の原料になるラウリン酸が石油の精製過程で得られたものなのか、ヤシ油由来のものなのか、成分表には記載されていないため、消費者は知ることができません。
界面活性剤以外で注目すべき成分とは?
シャンプーの成分は90%以上水と界面活性剤だと述べましたが、残りの10%はどのような成分で構成されているのでしょうか?その中で、チェックしておくべきものはあるのでしょうか?
賛否両論のあるシリコンやメントール、そして髪の発育に欠かせない保湿成分にも注目してみましょう。
シリコン
巷ではノンシリコンシャンプーが大流行していますよね。理由もわからないまま「シリコンは悪だ!」と思い込んでいる方も多いと思います。
しかし、シリコンは本当に悪なのでしょうか?
シリコンには、洗髪時 髪の摩擦を軽減してくれる役割があります。髪の長い女性の場合、シリコンが配合されているシャンプーを使った方が良いこともあるのです。
まずはシリコンの性質を理解しましょう。
シリコンは、油に馴染みやすい親油性という性質を持っています。
健康な髪の毛の表面は親水性なのでシリコンが付着することがありませんが、ダメージを受けてキューティクルが剥がれ落ちている部分は親油性なのでシリコンが付着しやすくなります。
そのため、シリコンが配合されているシャンプーを使うと、シリコンが髪のダメージ部分に付着して髪をコーティングすることで、艶を取り戻す効果を期待できます。
しかし、このダメージ部分に付着したシリコンは時間が経つと剥がれ落ちてしまい、その際に健康なキューティクルまで一緒にはがしてしまうことがあります。
こうなると、ダメージがいっそう進行してしまうので、ダメージがひどい場合はノンシリコンシャンプーをおすすめします。
また、シリコンが付着した部分はカラーやパーマがあたりにくくなる、という弊害もあります。
一時「シリコン入りのシャンプーは毛穴を詰まらせて薄毛の原因になる」という噂が流れましたが、これについては根拠が十分ではありません。
先ほども述べたようにシリコンは親油性、頭皮は親水性、つまりお互い間逆の性質なのでシリコンが毛穴に詰まることは考えにくいのです。
しかし、頭皮に汚れが残っている場合は話が違ってきます。汚れとはつまり油のことなので、シリコンが付着しやすくなります。
つまり、すすぎが不十分だと毛穴にシリコンがたまってしまう可能性があるのです。シリコン入りのシャンプーを使う場合は、頭皮をより入念にすすぐ必要があります。
ここまで シリコンの性質について説明してきましたが、ここでメリット・デメリットをまとめてみましょう。
メリット
洗髪時 髪の摩擦を軽減
デメリット
◎ダメージ部分に付着したシリコンが剥がれ落ちる際、健康なキューティクルまで一緒にはがしてしまうことがある。
◎ダメージがひどい髪には向かない
◎シリコンが付着した部分はカラーやパーマがあたりにくくなる
もちろんシリコンは化学物質なので、配合されてないに越したことはないのですが、どうしても避けたほうがいい成分と言うわけではありません。
自分の髪の長さやダメージ度合いを見た上で、ノンシリコンシャンプーを使うべきか否か検討してみましょう〜☆

界面活性剤は、洗浄効果を期待して配合されている成分です。シャンプー剤に配合されている界面活性剤は大きく5つに分類することができます。
高級アルコール系界面活性剤
アミノ酸系界面活性剤
ベタイン系界面活性剤(両イオン性界面活性剤)
ノニオン界面活性剤(非イオン性界面活性剤)
天然界面活性剤
界面活性剤の中には洗浄力の強いものと弱いものがありますが、洗浄力の強い界面活性剤は、色々と問題があります。
例えば、
◎頭皮や髪への刺激が強い⇒薄毛、頭皮の荒れの原因になる。
◎ 一緒に配合されている成分の効能をかき消してしまう。
◎ 頭皮の脂を取り過ぎてしまうので、不足した脂を補うため皮脂の分泌が盛んになる⇒結果、表面は脂ぎっているのに頭皮は乾燥している状態に⇒薄毛、頭皮の荒れの原因になる。
シャンプーは 水と界面活性剤でできているわけですから、シャンプー選びでもっとも大切なのは「どんな界面活性剤が使われているか」といっても過言ではありません。
では、以上に挙げた界面活性剤のうち、「洗浄力の強い界面活性剤」「適度な洗浄力の界面活性剤」はどれなのでしょう?
まずは界面活性剤の種類について、解説していきます。
高級アルコール系界面活性剤
市販の安価なシャンプーには、非常に洗浄力の強い高級アルコール系界面活性剤が配合されていることが多いです。
代表的なのが、
◎ラウレス硫酸Na
◎ラウリル硫酸Na
これらは、ヤシ油などに含まれるラウリン酸を原料にして作られた界面活性剤で生成過程で硫酸が使われます。
硫酸は非常に強い酸-皮膚や髪(タンパク質)を変性させてしまう刺激の強い成分です。また、洗浄力も強いため、頭皮の皮脂を過剰に除去してしまいます。
皮脂を過剰に除去してしまうと、頭皮は足りなくなった皮脂を補うために更に皮脂を分泌するようになり、その皮脂をまた除去して…という悪循環に陥ってしまうのですが、これが薄毛や頭皮の荒れの原因にもなるのです。
女性の場合、更年期に薄毛の悩みを抱える方も多いと思うのですが、薄毛が気になるなら ラウレス硫酸Naやラウリル硫酸Naが配合されているシャンプーは避けるべきでしょう。
ちなみに、同じくラウリン酸を原料にして作られた、
◎ラウレス-4カルボン酸Na
◎ラウレス-4酢酸Na
この2つは硫酸ではなく、弱い酸であるカルボン酸や酢酸(お酢)を使って生成されたものなので、比較的洗浄力もマイルドで刺激も弱い高級アルコール系界面活性剤です。
アミノ酸系界面活性剤
髪の90%はケラチンというタンパク質からできています。また、ケラチンというタンパク質は18種類のアミノ酸で構成されています。
◎ココイルグルタミン酸
◎ココイルアラニン
以上のように、成分名の中にアミノ酸の名前が含まれている界面活性剤はアミノ酸を原料として作られています。
グルタミン酸はケラチンの約13.7%、アラニンは2.8%を占めるアミノ酸です。
グルタミン酸には、他のアミノ酸の合成を助ける働きや髪のダメージ部分に吸着しコンディショニング効果を高める働き、またアラニンにはキューティクルが開かないようにする働き、頭皮のバリア機能を高める働きがあります。
ちなみに「ココイル」とは「ヤシ油から抽出した脂肪酸を用いている」という意味で、ココイルグルタミン酸の場合、ヤシ油から抽出した脂肪酸とグルタミン酸を原料にして作られた界面活性剤ということになります。
アミノ酸系界面活性剤は、髪の毛を構成するアミノ酸由来の成分に由来しているため、マイルドに洗い上げることができます。
ベタイン系界面活性剤(両イオン性界面活性剤)
◎ラウラミドプロピルベタイン
◎コカミドプロピルベタイン
成分名に「ベタイン」がついたものは、ベタイン系界面活性剤と呼ばれています。
別名 両イオン性界面活性剤とも呼ばれていて、その名の通り水に溶けると陰イオンにも陽イオンにもなる性質を持っています。
水がアルカリ性の場合は陰イオンに、酸性の場合は陽イオンになることで、水中の酸やアルカリを中和し、この作用により他の界面活性剤の洗浄力を低下させないようにする働きが期待できます。
そのため単独で配合されることはほとんどなく、他の界面活性剤の洗浄力を落とさないための補助剤として使用されることが多い界面活性剤です。
また、アミノ酸系界面活性剤より洗浄力が弱い分、刺激も弱いため皮膚の弱い方にもオススメできる界面活性剤です。
最近では、
◎ラウリルヒドロキシスルタイン
◎ラウラミドプロピルヒドロキシスルタイン
など、スルタイン系の両イオン性界面活性剤も見られるようになりました。(性質は、ベタイン系界面活性剤とほとんど同じです。)
ノニオン界面活性剤(非イオン性界面活性剤)
一番見分けにくいのが、このノニオン界面活性剤です。
代表的なものは、コカミドDEA のように、成分名の最後に「EA(エタノールアミンの略)」が付きます。
また、界面活性作用のある配糖体(糖を元にして作られた物質)を加えて、泡立ちを良くしている製品もありますが、これもノニオン界面活性剤に分類されます。
洗浄効果は穏やかで、水の硬度による影響を受けないため、メインの界面活性剤として配合されるよりも他の界面活性剤の補助的な役割で配合されることが多いようです。
天然界面活性剤
天然由来の界面活性剤には、
◎レシチン
◎サポニン
などがあります。
レシチンは卵黄に、サポニンは人参やヘチマやお茶に含まれている成分です。
天然由来の成分なので、比較的頭皮への刺激も弱く、これらの界面活性剤が配合されているシャンプーはマイルドな洗い心地となっています。
卵黄は良質なタンパク質からできているため、インドのアーユルヴェーダでは卵黄を頭皮に塗り、栄養を与えながら過剰な脂を取るという方法もあるくらいです。
また、界面活性作用はありませんが、殺菌作用のあるローズウォーターや洗浄力のあるクレイ(泥)が天然界面活性剤の代わりに配合されることもあります。
注意すべきはラウレス硫酸Na、ラウリル硫酸Na
今まで紹介した界面活性剤のうち、避けたほうがいいのは「高級アルコール系界面活性剤」です。
中でも、
◎ラウレス硫酸Na
◎ラウリル硫酸Na
この2つが配合されているシャンプーは要注意。
一般的に、この2つを「合成界面活性剤」と読んでいて、
合成界面活性剤 = ラウレス硫酸Naやラウリル硫酸Na = 頭皮、髪に悪い
と、私は考えています。
(厳密に言うと、高級アルコール系界面活性剤、アミノ酸系界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、ノニオン界面活性剤は全て「合成界面活性剤」に分類されるのですが、一般的に「合成界面活性剤 = ラウレス硫酸Naやラウリル硫酸Na」という認識が浸透しているようです。)
また、ラウレス硫酸Naやラウリル硫酸Naは「石油から作られた界面活性剤」と言われることもあります。
これらの界面活性剤の原料になるラウリン酸が石油を精製する際に分留される物質だからです。
しかし、界面活性剤の原料になるラウリン酸が石油の精製過程で得られたものなのか、ヤシ油由来のものなのか、成分表には記載されていないため、消費者は知ることができません。
界面活性剤以外で注目すべき成分とは?
シャンプーの成分は90%以上水と界面活性剤だと述べましたが、残りの10%はどのような成分で構成されているのでしょうか?その中で、チェックしておくべきものはあるのでしょうか?
賛否両論のあるシリコンやメントール、そして髪の発育に欠かせない保湿成分にも注目してみましょう。
シリコン
巷ではノンシリコンシャンプーが大流行していますよね。理由もわからないまま「シリコンは悪だ!」と思い込んでいる方も多いと思います。
しかし、シリコンは本当に悪なのでしょうか?
シリコンには、洗髪時 髪の摩擦を軽減してくれる役割があります。髪の長い女性の場合、シリコンが配合されているシャンプーを使った方が良いこともあるのです。
まずはシリコンの性質を理解しましょう。
シリコンは、油に馴染みやすい親油性という性質を持っています。
健康な髪の毛の表面は親水性なのでシリコンが付着することがありませんが、ダメージを受けてキューティクルが剥がれ落ちている部分は親油性なのでシリコンが付着しやすくなります。
そのため、シリコンが配合されているシャンプーを使うと、シリコンが髪のダメージ部分に付着して髪をコーティングすることで、艶を取り戻す効果を期待できます。
しかし、このダメージ部分に付着したシリコンは時間が経つと剥がれ落ちてしまい、その際に健康なキューティクルまで一緒にはがしてしまうことがあります。
こうなると、ダメージがいっそう進行してしまうので、ダメージがひどい場合はノンシリコンシャンプーをおすすめします。
また、シリコンが付着した部分はカラーやパーマがあたりにくくなる、という弊害もあります。
一時「シリコン入りのシャンプーは毛穴を詰まらせて薄毛の原因になる」という噂が流れましたが、これについては根拠が十分ではありません。
先ほども述べたようにシリコンは親油性、頭皮は親水性、つまりお互い間逆の性質なのでシリコンが毛穴に詰まることは考えにくいのです。
しかし、頭皮に汚れが残っている場合は話が違ってきます。汚れとはつまり油のことなので、シリコンが付着しやすくなります。
つまり、すすぎが不十分だと毛穴にシリコンがたまってしまう可能性があるのです。シリコン入りのシャンプーを使う場合は、頭皮をより入念にすすぐ必要があります。
ここまで シリコンの性質について説明してきましたが、ここでメリット・デメリットをまとめてみましょう。
メリット
洗髪時 髪の摩擦を軽減
デメリット
◎ダメージ部分に付着したシリコンが剥がれ落ちる際、健康なキューティクルまで一緒にはがしてしまうことがある。
◎ダメージがひどい髪には向かない
◎シリコンが付着した部分はカラーやパーマがあたりにくくなる
もちろんシリコンは化学物質なので、配合されてないに越したことはないのですが、どうしても避けたほうがいい成分と言うわけではありません。
自分の髪の長さやダメージ度合いを見た上で、ノンシリコンシャンプーを使うべきか否か検討してみましょう〜☆